はじめに
未就学児をお持ちの保護者様の中で、「このまま特別な教育をしなくていいのだろうか?」とか「小学校に入った時、まわりより遅れているのではないだろうか?」などと、心穏やかでいられなくなっている方はいらっしゃいませんか?
そこで、私も「幼児教育」「早期教育」は、塾講師として興味を持ち続けている分野なので、保護者様に分かりやすくお伝えしますね。
幼児教育とは?
 「幼児」とは、乳児期を過ぎた1歳から、小学校入学前の6歳までの時期をさします。
「幼児」とは、乳児期を過ぎた1歳から、小学校入学前の6歳までの時期をさします。
幼稚園や保育所も幼児教育に入りますが、「幼児教育」の概念には、それらに加え、家庭の教育や一部の知育教育も含まれます。幼児期は好奇心が旺盛で脳も柔軟なので、得意分野を見つけて伸ばすのに適しています。
また、この時期には言語能力や身体能力が著しく発達し、コミュニケーション能力や社会性を身に付け始めます。そのためこの時期に受ける教育は、生涯にわたる人格や能力の基礎、学習の土台となるためとても重要です。幼児期にバランスの取れた人間形成の基礎を身に付けることは、その後の健やかな成長に大きな影響を与えます。
「幼児教育」と「早期教育」
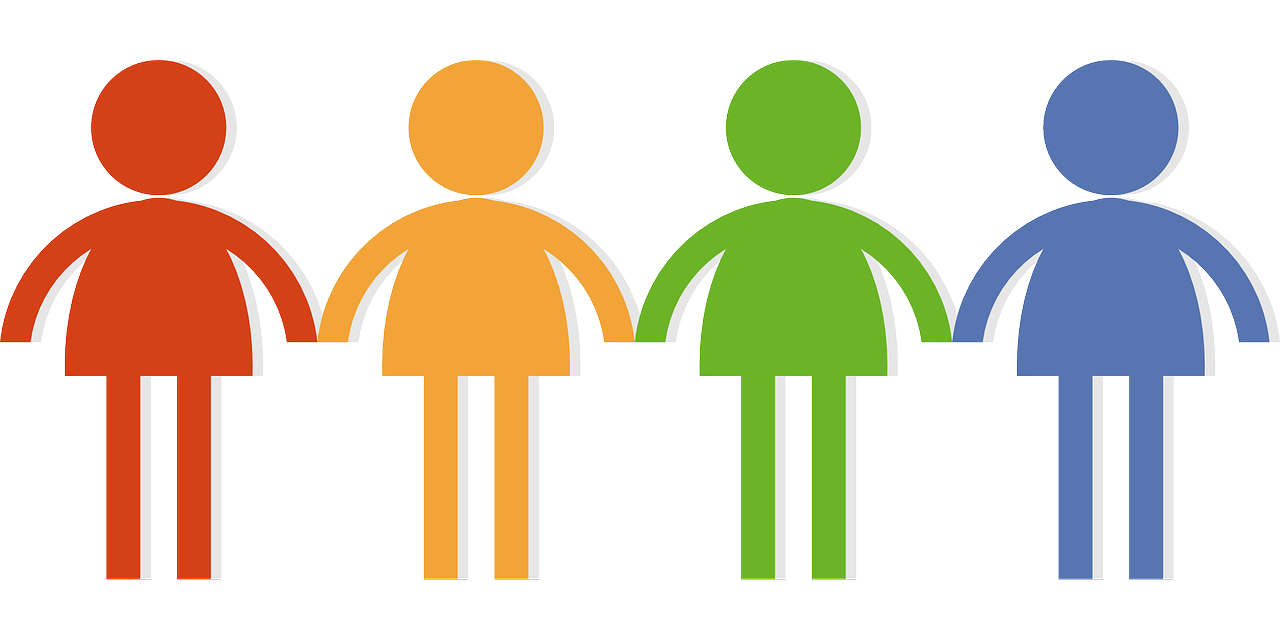 「幼児教育」と「早期教育」は「目的」が大きく異なります。「幼児教育」の目的が人格形成や学習の基礎づくりを重視しているのに対し、「早期教育」の目的は受験や専門的な技能の習得を目的としています。
「幼児教育」と「早期教育」は「目的」が大きく異なります。「幼児教育」の目的が人格形成や学習の基礎づくりを重視しているのに対し、「早期教育」の目的は受験や専門的な技能の習得を目的としています。
そのため、小学校受験などを見据えた早期教育では、知識の習得や学習の先取りを重視します。しかし幼児教育では、子どもの内面に働きかけ、目先の結果よりも、学習意欲や探求心などを培わせ可能性を伸ばすことを重視します。
幼児教育の種類
モンテッソーリ教育
 「モンテッソーリ教育」とは教育家のマリア・モンテッソーリが提唱したメソッドです。100年以上の歴史があります。子どもには「自分で自立に向かって成長していこうとする力」があることを前提としたメソッドです。子どもが自分で活動を自由に選び、納得するまで繰り返させることで「自発性」を重んじます。周囲の大人は、子どもが力を発揮できるような環境を整え、助ける役割を果たします。発達段階に合った教育環境や教具が用意されています。
「モンテッソーリ教育」とは教育家のマリア・モンテッソーリが提唱したメソッドです。100年以上の歴史があります。子どもには「自分で自立に向かって成長していこうとする力」があることを前提としたメソッドです。子どもが自分で活動を自由に選び、納得するまで繰り返させることで「自発性」を重んじます。周囲の大人は、子どもが力を発揮できるような環境を整え、助ける役割を果たします。発達段階に合った教育環境や教具が用意されています。
日本では、将棋の藤井聡太棋士も受けていた教育として有名になりました。
※「褒めて育てるとは」という私の記事も参考にしてください。
シュタイナー教育
 「シュタイナー教育」は哲学者であるルドルフ・シュタイナーが100年前に提唱したメソッドです。0歳から21歳までを7年ずつ3つの成長過程に分類し、発達段階に合わせた教育を行うのが特徴です。
「シュタイナー教育」は哲学者であるルドルフ・シュタイナーが100年前に提唱したメソッドです。0歳から21歳までを7年ずつ3つの成長過程に分類し、発達段階に合わせた教育を行うのが特徴です。
幼児期に重視するのは健康な「からだ」を育てることで、手足をたくさん動かして遊ばせます。大人は規則正しい生活のリズムや温かみのある環境を整え、子どものペースに合わせた成長を助けます。「意思」や「創造力」を育み、自分の意思に基づいて自由に行動できるように育てることが目的です。
児童文学作家のミヒャエル・エンデや、日本では俳優の斎藤工さんがシュタイナー教育を受けて育ちました。
レッジョ・エミリア・アプローチ教育
 「レッジョ・エミリア・アプローチ教育」は、米国大手企業の社内プリスクールでも取り入れられている教育法です。子どもの個性や意思を尊重し、それらを最大限に生かすのが特徴で、子どもが体験を通して自分自身で学んでいくスタンスです。
「レッジョ・エミリア・アプローチ教育」は、米国大手企業の社内プリスクールでも取り入れられている教育法です。子どもの個性や意思を尊重し、それらを最大限に生かすのが特徴で、子どもが体験を通して自分自身で学んでいくスタンスです。
具体的には、話し合いを通して、子どもの自ら考える能力やコミュニケーション能力を高めます。また、グループを作って共同作業に取り組むことで、「自主性」だけでなく、周囲の意見にも耳を傾ける「協調性」も身に付けられます。
ピラミッドメソッド
 「ピラミッドメソッド」は、オランダ政府教育評価機構Cito(チト)が提唱した幼児教育メソッドです。
「ピラミッドメソッド」は、オランダ政府教育評価機構Cito(チト)が提唱した幼児教育メソッドです。
子どもが安心できる環境をつくり、子どもだけでなく保育者の自主性も育まれるのが特徴です。子どもたちの「自分で決断する力」や「自己解決能力」を育て、あらゆる領域において、認知的・身体的・社会情緒的にも、バランスの良い発達を促します。さらに、子どもたちは楽しみながら「創造力」を身に付けることもできます。
ドーマンメソッド
 「ドーマンメソッド」とは、アメリカで人間能力開発研究所を創設したグレン・ドーマンが用いたメソッドです。乳幼児期の子どもたちに適切な刺激を与えることで可能性が伸びることに気づいたのです。
「ドーマンメソッド」とは、アメリカで人間能力開発研究所を創設したグレン・ドーマンが用いたメソッドです。乳幼児期の子どもたちに適切な刺激を与えることで可能性が伸びることに気づいたのです。
赤ちゃんの頃からあえて算数や文字、水泳などを積極的に学ばせます。理解力や判断力が高く、好奇心が旺盛なだけでなく、穏やかで思いやりがあり、自分の意見をしっかり言えるような子どもに育てることが目的です。
ニキーチン教育
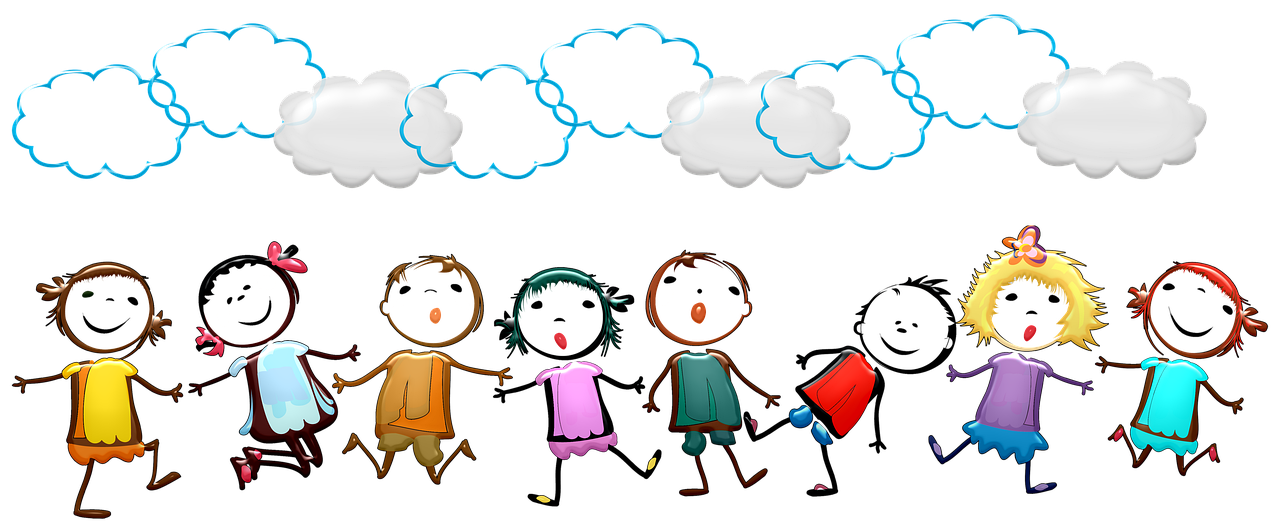 「ニキーチン教育」は、ニキーチン夫妻が7人の子どもたちを育てる中で実践し、提唱したメソッドです。
「ニキーチン教育」は、ニキーチン夫妻が7人の子どもたちを育てる中で実践し、提唱したメソッドです。
「創造力」を身に付けさせるため、「自分で考える力」や「自分で解決法を見つけ出す力」を育むことを重視します。子どもたちは遊びを通して、比較対照して分析する能力や、物事の法則を見つけたり組み合わせたりする能力などの知的能力を養うことができます。
石井式教育法
 「石井式教育法」は、教育学者である石井勲博士によって提唱されました。幼時期に適切な言語教育を行うことで可能性を伸ばします。
「石井式教育法」は、教育学者である石井勲博士によって提唱されました。幼時期に適切な言語教育を行うことで可能性を伸ばします。
言葉は思考の土台で、豊かな表現力はコミュニケーション能力や理解力の向上にもつながるからです。豊かな言葉が豊かな心を育むことを目指して漢字教育を行います。
ヨコミネ式教育法
 「ヨコミネ式教育法」とは横峯吉文氏が提唱するメソッドです。「正義感や道徳観」、「体力や柔軟性」、「経験や勉強を通して自ら知識や生きる知恵を学ぶ力」を育むことで、子どもたちが持つ可能性を引き出します。その結果自ら考え、行動できるようになることが目的です。
「ヨコミネ式教育法」とは横峯吉文氏が提唱するメソッドです。「正義感や道徳観」、「体力や柔軟性」、「経験や勉強を通して自ら知識や生きる知恵を学ぶ力」を育むことで、子どもたちが持つ可能性を引き出します。その結果自ら考え、行動できるようになることが目的です。
基礎学習や運動の分野などで、その子にとっての「少し難しい」課題を与えることで、能力を引き出していきます。
フィギアスケーターの紀平梨花さんもヨコミネ式を取り入れた幼稚園に通っていました。
七田式教育法
 「七田式教育法」は、世界平和功労騎士勲章を受章した七田眞氏が提唱したメソッドです。右脳教育を積極的にとり入れます。
「七田式教育法」は、世界平和功労騎士勲章を受章した七田眞氏が提唱したメソッドです。右脳教育を積極的にとり入れます。
また、知識や理性の教育だけでなく、人間として心を豊かにすることや感性の教育も重視しています。大きな夢や志を持ち、リーダーシップをとれる子どもを育てることが目標です。
池江 璃花子さん(水泳)、本田真凜さん(フィギュアスケート)、本田望結ちゃん(女優・フィギュアスケート)なども、七田式の卒業生です。
幼児教育で大切なこと
子どもの自主性を育てる
 幼児教育では、子どもの自主性を育てることが大切です。親の意思や思い入れに子どもを巻き込むのは避けたいものです。子どもたちは興味あることには時間を忘れて取り組みますが、強制されたことには集中できないし、身に付きません。
幼児教育では、子どもの自主性を育てることが大切です。親の意思や思い入れに子どもを巻き込むのは避けたいものです。子どもたちは興味あることには時間を忘れて取り組みますが、強制されたことには集中できないし、身に付きません。
保護者様は、子ども自身がやることに興味・関心を持ってください。自分のお子さんをよく観察することが大切です。そうすれば、子どもが何を望んでいるか、得意なことは何かなどが自然と理解できるので、子どもに合った幼児教育を無理なく選ぶことができます。
幼児教育は親子で取り組む
 幼児教育は、親子で取り組むことが大切です。幼児教室や保育園の施設だけではありません。家庭でも子どもは多くのことを学んでいます。絵本の読み聞かせ、お絵かき、ボール遊びなども幼児教育なのです。お片付けなどを頼むのも良いでしょう。「教育」というと、子どもにだけ焦点があたりがちですが、親子で一緒に学ぼうとする姿勢が大切です。一緒に取り組むことで子どもはより楽しさや喜びを感じます。また、親から褒められる経験は関心事を広めたり意欲を高めたりすることにもつながります。
幼児教育は、親子で取り組むことが大切です。幼児教室や保育園の施設だけではありません。家庭でも子どもは多くのことを学んでいます。絵本の読み聞かせ、お絵かき、ボール遊びなども幼児教育なのです。お片付けなどを頼むのも良いでしょう。「教育」というと、子どもにだけ焦点があたりがちですが、親子で一緒に学ぼうとする姿勢が大切です。一緒に取り組むことで子どもはより楽しさや喜びを感じます。また、親から褒められる経験は関心事を広めたり意欲を高めたりすることにもつながります。
将来、役に立つことを身につける
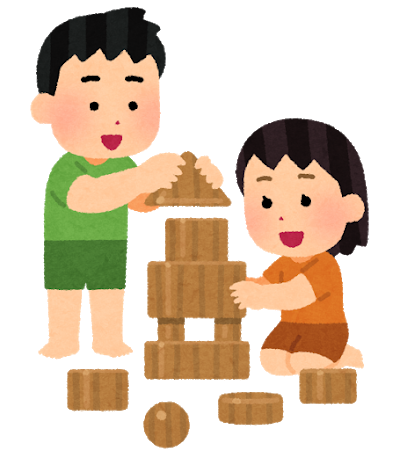 幼児教育の役割の1つは、就学後の生活に向けた準備をすることです。例えば、小学校に入ると集団行動が発生するため、まずは集団生活のルールを学ぶことが大切です。自分の考えを相手に伝えることや、人の話をちゃんと聞くことはとても大事なことです。また、あいさつなどの生活習慣やマナーも、しっかり身に付けておきたいものです。
幼児教育の役割の1つは、就学後の生活に向けた準備をすることです。例えば、小学校に入ると集団行動が発生するため、まずは集団生活のルールを学ぶことが大切です。自分の考えを相手に伝えることや、人の話をちゃんと聞くことはとても大事なことです。また、あいさつなどの生活習慣やマナーも、しっかり身に付けておきたいものです。
成功体験がやる気にさせる
 幼児教育を通して、子どもが何かを達成できたときには、その都度、一緒に喜んだり褒めたりして、子どもが「達成感」を得られるようにしましょう。達成感や成功経験は、子どもにとっての自信につながります。これからの人生でさまざまなことを学んでいくにあたり、自信は新しいことに挑戦する意欲にもなります。失敗したときやうまくいかなかったときには、またチャレンジできるように励ましてあげましょう。
幼児教育を通して、子どもが何かを達成できたときには、その都度、一緒に喜んだり褒めたりして、子どもが「達成感」を得られるようにしましょう。達成感や成功経験は、子どもにとっての自信につながります。これからの人生でさまざまなことを学んでいくにあたり、自信は新しいことに挑戦する意欲にもなります。失敗したときやうまくいかなかったときには、またチャレンジできるように励ましてあげましょう。
最後に
 幼児教育にはさまざまなメソッドがあり、それぞれに特色があります。大切なのは、保護者様の子どもに合った方法で能力を伸ばしてあげることです。人格形成や学習の土台を築く大切な時期を有効活用して、その後の人生の備えがしっかりできるようにサポートしてあげましょう。くれぐれも以下のことには気をつけましょうね。
幼児教育にはさまざまなメソッドがあり、それぞれに特色があります。大切なのは、保護者様の子どもに合った方法で能力を伸ばしてあげることです。人格形成や学習の土台を築く大切な時期を有効活用して、その後の人生の備えがしっかりできるようにサポートしてあげましょう。くれぐれも以下のことには気をつけましょうね。
「否定しないこと」
「比較しないこと」
「個性を受け入れること」
「急がないこと」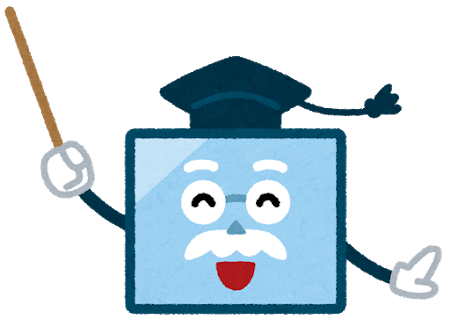 (take_futa)
(take_futa)
白(大).png)


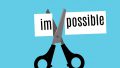
コメント