はじめに
以前、他の記事でも「褒めて育てる」ことに触れたことがありました。
<元塾講師が教える塾通いの目的>生徒の褒め方
この記事は「塾通いの目的」が主軸だったので、「褒めて育てる」ことに関しては、残念ながら深堀りはできませんでした。ただ、このキーワードが、心のどこかに引っかかっていたので、いろいろ調べてみると、かなり深刻な教育問題に発展していて、驚いてしまいました。今回は「褒めて育てる」ことに焦点を当てて、深堀りしてみたいと思います。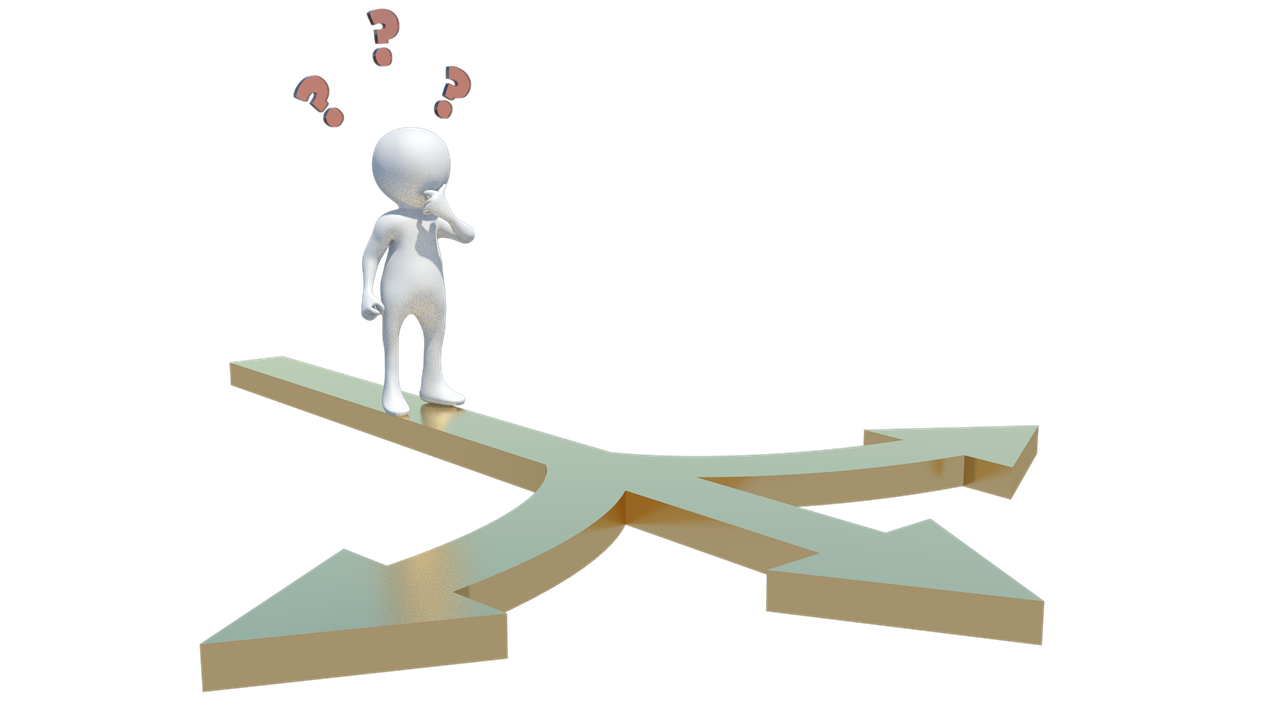
「褒めて育てる」ことに関しては賛否両論あるようです。「スパルタ教育」がもてはやされた時期があったり「褒めて育てる教育」が時流に乗った時期もあります。この記事では、どちらがいいのかという視点ではなく、「褒めて育てる」ことのメリットとデメリットを、実験や論文など可能な限り客観的なものを根拠に論じてみたいと思います。
私は塾講師として現場で40年近く子どもたちと接してきて、「子どものリアルな変化」は肌で感じています。その変化が何によるものなのかは、今のところ私にもわかりませんが、「教育」が関係している可能性は大きと思っています。
「褒めて育てる」ことは正しいという意見
「ほめること」と「運動技能の取得」の成果についての検証実験
自然科学研究機構生理学研究所・定藤規弘教授、名古屋工業大学・田中悟志准教授らが、東京大学先端科学技術研究センターの渡邊克巳准教授の協力の下、行った実験。
<実験方法>
(1日目の実験)
パソコン画面に表示される1~4の4つの数字に合わせて、手元の4つのキーをピアノの
鍵盤のように30秒間速くたたく。30秒間の休憩をはさみ、12回実施。
48人の成人男女。トレーニング終了後、3つのグループに分ける。
Aグループ=「自分が評価者からベタほめされる」グループ
Bグループ=「他人が評価者からほめられるのを見る」グループ
Cグループ=「自分の成績だけをグラフで見る」グループ
注意点 褒め方はポジティブに
評価者がその分野のエキスパート
褒める内容 1.パフォーマンス 2.態度 3.性格 を具体的に褒める
(2日目の実験)
再度、同じトレーニングを実施する。
1日目と2日目の成績を比較する。
<実験結果>
Aグループ=「自分が評価者からベタほめされる」 : 成績が20%伸びた
Bグループ=「他人が評価者からほめられるのを見る」 : 成績が14%伸びた
Cグループ=「自分の成績だけをグラフで見る」 : 成績が14%伸びた
この6%の数値の差は、統計学的に明らかに有意性があることを立証するものです。
褒めることで運動技能の習得性が高まったことの科学的な証明となりました。
<この実験の背景と考察>
この実験の背景には、定藤教授らのある研究成果があります。それは、fMRI(機能的核磁気共鳴)を使って脳の反応を調べた研究で、「報酬」として金銭をもらったときに反応する脳の部位と、ほめられたときに反応する脳の部位が、同じ腹側線条体という部分であることを突き止めたものです。つまり、「褒められること」は「報酬」なのです。
ほめられて気分がいいのはドーパミンの効果です。脳科学の分野では、報酬を受け取ることによって腹側線条体が反応した際に、同時にドーパミンという脳内物質が分泌されることが知られています。これは、いわゆる快楽物質と呼ばれる神経伝達物質の一種で、ドーパミンが記憶の定着化と運動技能の制御の両方にも深く関与していることがわかっています。
これらの事実から推測されることは、ほめられることによってドーパミンが分泌され、運動技能に関する記憶がより強固に定着され、その結果、学習効果が高まるというシナリオです。これが、「ほめられると伸びる」の正体ではないかと思われます。
また、定藤教授はつねづね「ほめることは、薬と一緒だ。」ほめることの要領(用量)と用法を間違えると、依存症などの副作用を起こしかねないと言っています。
たとえば、報酬の副作用としては、アンダーマイニング効果が知られています。これは、元々好きで自発的にやっていた行為に対して、いったん報酬を与え、次に与えるのを止めてしまうと、行為に対するやる気が起きなくなってしまうという現象です。
この副作用は、「褒めて育てる」ことの難しさを語っています。後にご紹介する「ほめると子どもはダメになる」という意見の根拠になるのかもしれませんね。
ポジティブ・フィードバック
臨床心理学の世界では、ポジティブ・フィードバックといって、相手にとって望ましい評価を与えることで学習効果が高まることが知られています。
そして、臨床の現場でも導入されていますので、科学的に実証済みです。
そのことから導き出されるのは、
「子どもを褒めて育てると、自分に自信を持ち、さまざまなことにチャレンジできる子どもに育つ」
また、自尊心が高い(自分に自信を持っている)生徒は、教員との関係が良好で、学習意欲が高く、実力に見合った進路を選択する傾向があることも報告されています。
東大生へのアンケート
〇 東大生184人への質問
「親は自分の話を聞いてくれましたか?」 9割以上がYES
「よく褒めてくれましたか?」 82%がYES
開成・柳沢校長の教育論から引用
たとえば、子供の音読の声が「ちょっと小さいな」と感じたとします。そのとき、「もっと大きな声を出しなさい」と、否定的な言葉で伝えるのと、「上手だね。もう少し声が大きいと、もっと良くなるよ」と褒めるのでは、受け手である子供の気持ちは全然違います。
<褒め方に注意が必要>
「いつも100点で偉いね」という褒め方は、結果を褒めています。言い方を変えて「100点を取るなんでなかなかできないよ。頑張ってるね」とすると、褒めるポイントが結果ではなく過程になるので、子どもの意欲を上手に育てます。
<叱ることも必要>
子供たちは日々いろいろやらかすので、必要に応じて毅然と叱らねばならない時もあります。
また、褒めっぱなしではなく「課題を与え」成長を促すことも必要です。スモールステップで課題を急ぎ過ぎず与えるのも親の役目です。
ミューラー教授(コロンビア大学)の「褒め方に関する実験」から
コロンビア大学のミューラー教授らは、ある公立小学校の生徒を対象にして「褒め方」に関する実験を行いました。
ミューラー教授らは、子どもたちをランダムにAクラスとBクラスの2つのグループに分けました。
<実験方法>
>> A・B両方のグループの生徒が比較的簡単なIQ テスト(1回目)を受けました。
>> Aグループの生徒に対しては、テストの結果がよかったときには「あなたは頭がいいのね」と、子どもたちのもともとの能力を称賛するメッセージを伝えました。
>> Bグループの生徒に対しては、「あなたはよく頑張ったわね」と、努力を称賛するメッセージを伝えました。
>> その後、ミューラー教授らは、同じ子どもたちに、かなり難しめのIQ テスト(2回目)を受けさせました。
>> さらにその後、最初に受けたのと同じ程度のIQ テスト(3回目)を受けさせました。
<実験結果>
<3回目のテストの結果>
Aクラスの「もともとの能力を褒められた子どもたち」は成績を落としました。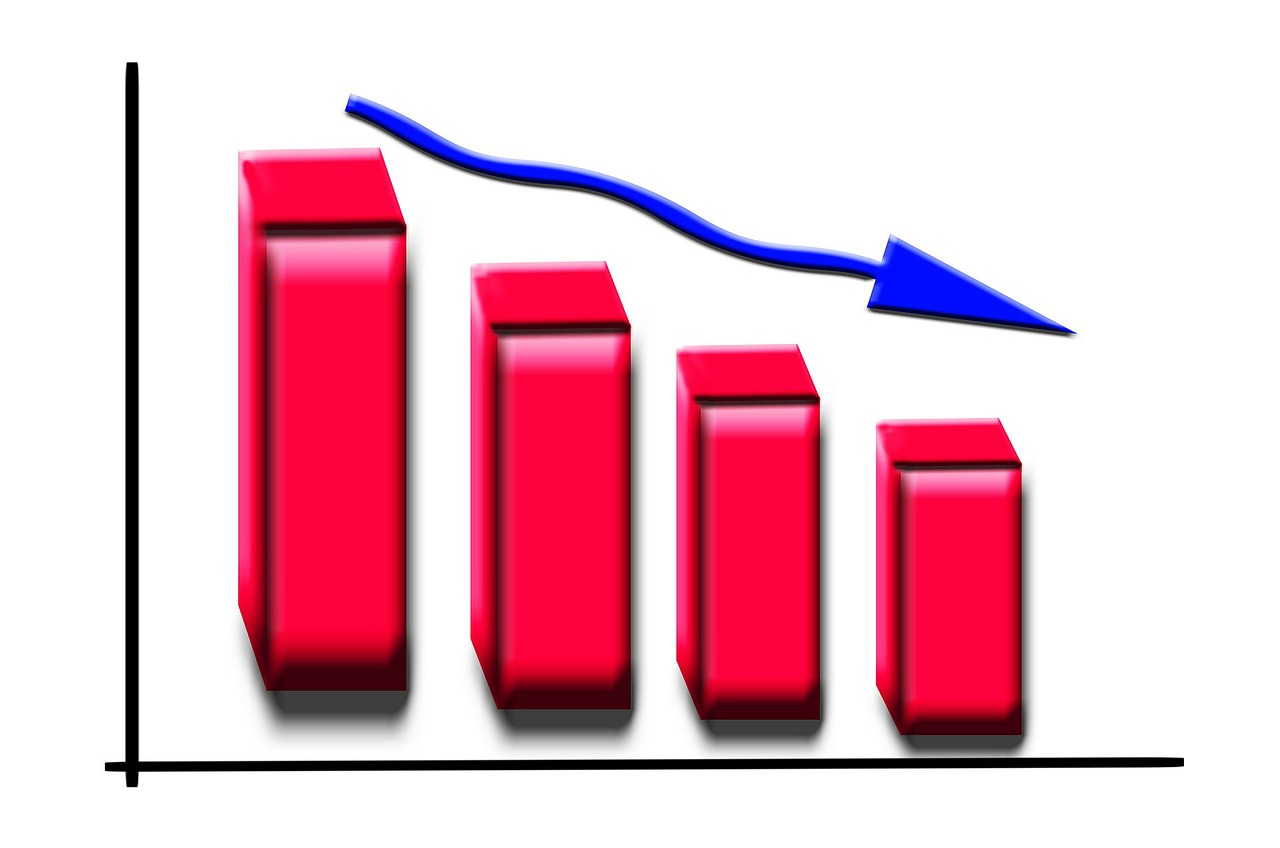
Bクラスの「努力を褒められた子どもたち」は成績を伸ばしました。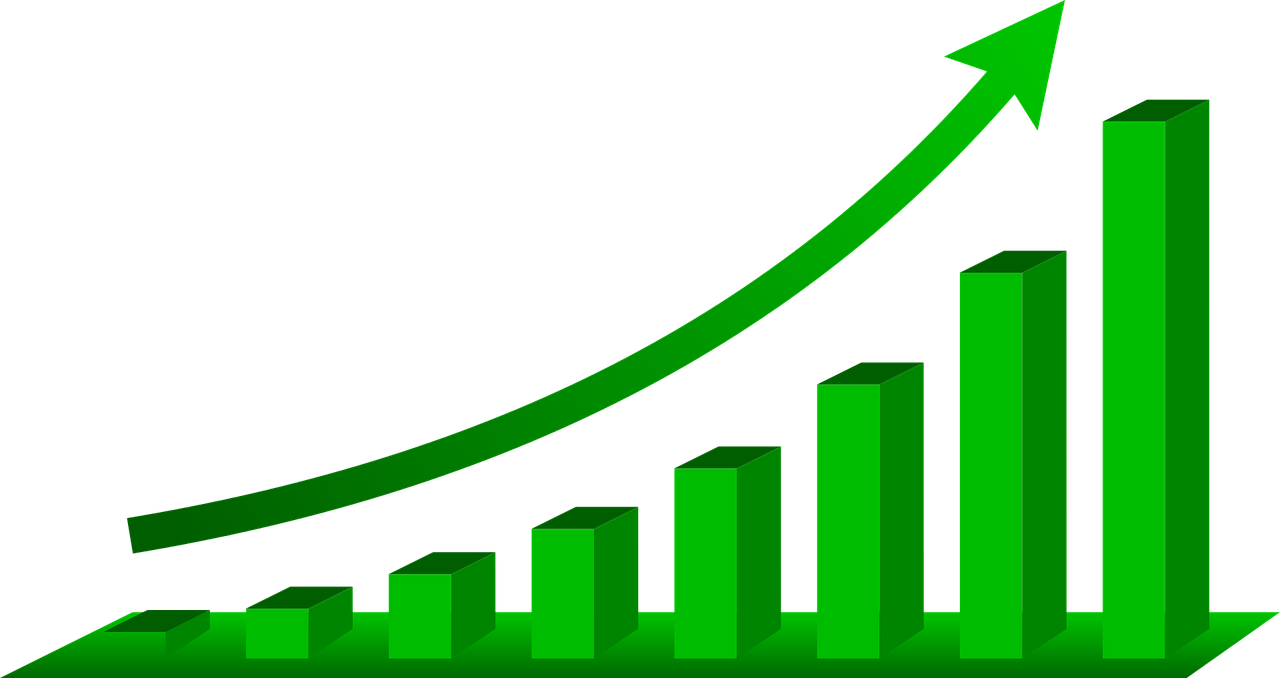
<実験の考察>
Aクラスの生徒は、
2回目の難しめのIQ テストを受ける際、この試験のゴールは「何かを学ぶこと」ではなく、「よい成績を取ること」にあると考えたのです。
また、テストでよい点数が取れなかったときには、成績を高く偽るウソをつく傾向があることもわかりました。
また、彼らは、よい成績が取れたときはその理由を「自分に才能があるからだ」と考え、同じように、悪い成績を取ったときも「自分に才能がないからだ」と考える傾向がありました。
Bクラスの生徒は
2回目、3回目のテストでも粘り強く問題を解こうと挑戦を続けました。努力を褒められた子どもたちは、悪い成績を取っても、それは「(能力の問題ではなく)努力が足りないせいだ」と考えたようです。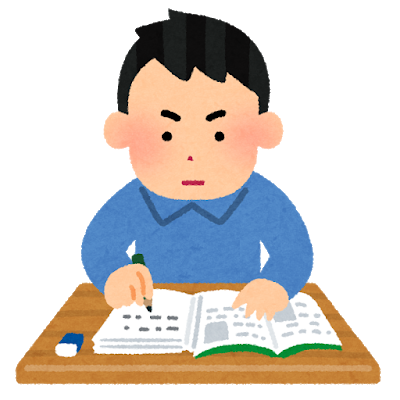
この実験結果が教えてくれるのは、褒める時には「才能」ではなく「努力」を褒めるべきだということです。
また、具体的に子どもが達成した内容を挙げることも重要であるということもこの実験でわかりました。例えば、
「昨日は、試験の勉強を夜遅くまでやっていたね。」とか、
「算数の計算問題集を全部済ませておいてよかったね。」などです。
そうすることによって、さらなる努力を引き出し、難しいことでも挑戦しようとする子どもに育つのです。
「褒めて育てる」とこどもをダメにするという意見
「褒める」「叱る」ことを否定している「アドラー心理学」とは
それは子育てや教育現場だけでなく、社会人になってからの部下の教育や夫婦、友達同士、恋人同士といった全ての関係に当てはまります。なぜアドラー心理学では「褒めること」を推奨していないのでしょうか?
賞罰教育の否定
アドラーは賞罰教育を否定しています。
「褒めることは相手の自立心を阻害し、褒められることに依存する人間を作り出してしまうから」とアドラーは言っています。
「好ましい行動をとった時に褒め、そうではない時に叱る」という行為をくりかえすたびに、「褒め言葉」に依存し、いつの間にか他者のコントロール下におかれてしまうのです。
そして、褒めてくれる人がいるならやる、でも、いなければやらない、という考え方に行きついてしまいます。
「褒める」という行為は基本的には上から下への評価という側面を持ちます。アドラー心理学で推奨されているのは「横から(=対等の関係で)勇気づける。」なのです。
課題の分離とは
子どもには子どもの、部下には部下の、友人には友人の、それぞれの「課題」があります。そこへ立ち入ってはいけない、という「課題の分離」はアドラー心理学の軸となる考え方です。
例えば、子どもが宿題をこなそうと夜遅くまで頑張っていたとき、その宿題は誰の「課題」だろうと考えます。それは当然「子どもの課題」です。課題とはその事柄を最終的に引き受ける人物のものであるという考え方です。そして、アドラー心理学では、たとえ親であっても、人の課題にむやみに踏み込まないと教えています。
あらゆる人間関係が破たんしていく大きな原因の1つは「課題の分離ができていない」からだと、アドラーは教えています。
「褒める・叱る」より「援助」を
相手との関係を「相手は下だ」との認識があるから、「褒める・叱る」ことをして他者への課題に土足で踏み込もうとするのです。
たとえば、相手の状況や立場で(子ども、年下、部下、初心者)未熟な存在に見えてしまうかもしれませんが、その関係は対等でなければなりません。
褒める・叱るは上下関係、「援助」は対等な関係です。
では、「援助」とはどのような行為かといいますと、
• 相手に必要な情報を提供すること
• 相手をサポートする意思があることを伝えること
• 相手が助けを求めてきたときに、必要な援助をすること
• 失敗をとがめないこと、そこから学んだことを認める
• 評価ではなく感謝の気持ちを伝える
このような手助けは相手を勇気づけることにつながります。
褒めることは依存心の強い人間を作る
さらにアドラー心理学では「褒めることは依存心の強い人間を作る」と主張しています。人を褒めることが良いことだと思い、次から次へと褒め言葉を他者に与えることは、依存心の強い人間に付きまとわれる原因にもなります。
良かれと思って褒めても、相手にとってもあなたにとってもマイナスの効果しか得られないケースもあることは意識しておきたいものです。
モンテッソーリ教育の子育て
 「モンテッソーリ教育」とは教育家のマリア・モンテッソーリが提唱したメソッドです。100年以上の歴史があります。子どもには「自分で自立に向かって成長していこうとする力」があることを前提としたメソッドです。
「モンテッソーリ教育」とは教育家のマリア・モンテッソーリが提唱したメソッドです。100年以上の歴史があります。子どもには「自分で自立に向かって成長していこうとする力」があることを前提としたメソッドです。
「モンテッソーリで子育て支援 エンジェルズハウス研究所」の田中昌子先生の、子育て相談を引用させていただきました。
モンテッソーリ教育の考え方を見てみましょう。
大人が子どもを評価せず、子ども自身が上手にできたことを判断することで、本当の意味での自己肯定感が育つ
具体的には、子どもが何かに興味を持ち、そのことに集中し始めたときには、一切の介入をしないようにすることが重要です。ともすると、大人はそういうときに「頑張っているねえ」とか「すごいねえ」と思わずほめてしまいそうになりますが、それが集中を妨げてしまうもとになります。
子どもが満足してお仕事を終えたときには、拍手をしたり「頑張ったねえ」「すごいねえ」と言葉に出して言ったりするのではなく、微笑み、認めてあげるだけで十分です。モンテッソーリは、精神的な魂の静けさを贈る、と表現しています。
ですから、トイレに行く、ご飯を食べるといった人間として当たり前にすることについては、「できたね」と認め、共感してあげればよいことで、あえて大げさにほめる必要はありません。そこをほめてしまうと、ほめられることが目的になってしまいがちです。
どうしても言葉に出して何か言いたいというときには、「お皿を丁寧に洗ったね」「ごはんを残さず食べたね。」のように、事実をありのままに言うことをお勧めします。
これは、子どもを評価しないことにつながります。大人はどうしても子どもを評価しがちです。しかし、自分が上手だったかは、本来子ども自身が判断すればよいことで、子ども自身が一番理解できていることなのです。
そうして育つのが本当の意味での自己肯定感です。大人がいくら言葉を尽くしても、言葉だけで自己肯定感を育てることはできません。
自分自身を創りあげた子どもは、ほめるという大人の評価やご褒美が不要になる
ほめたりご褒美をもらったりということに慣れてしまった子どもは、それがないと、当然ですがやらなくなります。常に大人の顔色をうかがったり、評価を気にしたりするようにもなります。特にご褒美は、どんどん高いものを要求するようになります。また、ちょっとうまくいかなかったり、失敗したりすると、極端なまでに落ち込んだり、もうやらないとふてくされてしまいます。
モンテッソーリ教育では子どもの活動をお仕事と呼びますが、自分自身を創りあげていくという崇高なお仕事をやり終えた子どもは、ほめるという大人の評価やご褒美が不要になるのです。
モンテッソーリは子どもたちがお菓子や飾りといった褒美を突き返す、といった様子を著書にたびたび書いています。
「ほめると子どもはダメになる」の著者で有名な榎本博明氏の意見
「褒めて育てる」でダメになった日本の若者
榎本氏は、頑張れず、傷つきやすい現代の若者たちは、日本の文化風土を無視したエセ欧米流の「褒めて育てる思想」の産物であるといいます。著書『ほめると子どもはダメになる』でこうした現実を指摘した臨床心理学者で、MP人間科学研究所代表の榎本博明氏の意見を引用します。「褒めて育てる」にはさまざまな歪みがあると榎本氏は言います。
※可能な限り榎本氏の表現を尊重して「引用」します。過激な表現があるかもしれませんが、ご容赦ください。
なぜ、若者の「生きる力」が衰えてしまったのでしょう。
褒められるのが当たり前になって育つと、きついことは言われません。それは欧米流の「褒めて育てる」を歪んだ形で導入したからです。暗黙の関係性や一体感で動く日本人と欧米人との差は大きいのです。親子関係や夫婦関係に端的に表れています。 たとえば、食べ物の好き嫌いが激しい子どもに食べさせる場合です。まず「食べなさい」と命じるのは共に同じです。それで食べないと、米国の親ならば、語調を強めて「食べなさい!」と強硬に出る。ところが日本人の親は、「お願いだから食べて」と、お願い調に転じる。さらには「明日は食べるよね」と譲歩して、それでも食べないと「もういい」とキレます。
たとえば、食べ物の好き嫌いが激しい子どもに食べさせる場合です。まず「食べなさい」と命じるのは共に同じです。それで食べないと、米国の親ならば、語調を強めて「食べなさい!」と強硬に出る。ところが日本人の親は、「お願いだから食べて」と、お願い調に転じる。さらには「明日は食べるよね」と譲歩して、それでも食べないと「もういい」とキレます。
欧米と日本の文化の根底の違い
欧米ではすべて言葉とスキンシップでのコミュニケーションです。日本人には心理的な一体感が形成されているので言葉なしでも通じます。その文化の根底の違いが加わって「褒めて育てる」はさまざまな歪みを引き起こすと、榎本氏は考えます。
「褒めて育てる」が推奨されて、20年を超えます。
1990年代から推奨されて、それと並行して、学校教育でも新学力観が適用されました。それまでの競争による知識偏重をやめて授業中の態度や関心で成績を決める方向です。
態度や関心でのプロセスを評価するとなると、ついつい自分に対していい態度を取る人に対して評価を高くしてしまうものです。日本人はとかく関係性で動くから、大人の社会の人事評価自体もうまくいっていないのですが、それが学校にまで持ち込まれたのです。
褒められるのが当たり前になる子どもたち
褒めまくられて育てられると、褒められるのが当たり前になります。逆に褒められないとやる気がなくなってしまうのです。「褒めてくれないと自分たちはめげる世代だ」と言う若者も多いのです。学生時代はそれで通るかもしれませんが、社会に出てそれが通るわけがありません。
褒められ続けると、その状態を維持しなければいけなくなってきます。難しい課題にチャレンジしたら失敗するかもしれません。褒められ続けるポジションから落ちたくないので、確実に褒められる得意な課題に限って取り組み、難しい課題は初めから避けるようになってしまいます。
その結果、難題にチャレンジして本人が鍛えられるということがなくなります。一方、褒められてばかりだと、しかられなくても注意されただけで自分が全否定されたように受け取って、怒り出したり落ち込んだりする気質になってしまいます。
褒めて育てるのは「自己肯定感」を養うためだったのでは?
自分の力で壁を乗り越えていくことを経験して初めて自己肯定感は高まります。頑張ってもいないのにただ褒められていい気持ちになっていたのでは、本当の自己肯定感は育ちません。ただおだてられて育てられてきたから、がつんとやられたらぽしゃんとなります。だから自己肯定感は低いのです。 本当の自信をつけさせるには、子どもを信じて鍛える体当たりの子育てから始めるべきではないでしょうか。特に幼少期には、たとえば歩き始めたとき、当然親は褒めます。厳しい壁を作りつつ、褒めるときは褒める、でいいのではないでしょうか。何でも褒めてしからない子育てではダメなのです。何かの折に褒めることは当然ありますが・・・。
本当の自信をつけさせるには、子どもを信じて鍛える体当たりの子育てから始めるべきではないでしょうか。特に幼少期には、たとえば歩き始めたとき、当然親は褒めます。厳しい壁を作りつつ、褒めるときは褒める、でいいのではないでしょうか。何でも褒めてしからない子育てではダメなのです。何かの折に褒めることは当然ありますが・・・。
最後に
「褒めて育てる」の賛成意見、反対意見を分け隔てなく載せたつもりです。賛成意見の方は客観的な「実験」で説明がなされていました。しかし、反対意見の方は実験が少なく、「褒めて育てる」のアンチテーゼのような意見が多いと感じました。
しかし「褒めて育てる」の賛成意見の実験結果や考察を見てみると、全面的な賛成ではなく、「褒め方に対する注文!」が数多く見られました。また、反対意見の方は「褒めて育てる」だけでは、ダメであるという意見が主流です。つまり、「褒めて育てる」ことを全面的に反対しているわけではないのです。
総合的に考えると、白黒はっきりつけましょうというような対立ではないと感じました。どちらの立場をとっても、子どもをしっかり見続けていなければできない事ばかりです。褒めるにしても、かなり状況を把握して、言葉を選ばなければならないのです。なんでもかんでも「褒めちぎる」のはどちらの立場の方も反対しています。
今ではある年齢の方しかご存知ではないかもしれない石原慎太郎の著書『スパルタ教育』(1969)が70万部の大ベストセラーでした。このスパルタ式教育の大波の後に1992年から実施された学習指導要領に採用された「新学力観」ゆとり教育の影響か「褒めて育てる」教育が主流を奪い、2013年に出版されたアドラー心理学を解説した著書『嫌われる勇気』や『ほめると子どもはダメになる』榎本博明著(2015)あたりから、「褒めて育てる」に陰りが見えてきました。
服の流行とは当然、質も周期も異なるかもしれませんが、教育メソッドにも流行りすたりがあるのを感じました。私たちはその流行っているメソッドを子どもにそのまま当てはめるのではなく、その方法のいい部分だけを取り入れた教育をわが子に与えるのが正しい選択だと思います。今のメソッドも20年経てばアンチテーゼのメソッドに取って代わられるのです。
親御さんは、賢い選択をしてください。自分たちに合った子供の育て方は、千差万別です。周りに流されないでください。今回の記事はいろいろな有識者の皆さんの意見をずらりと並べた形を取っています。是非とも、その中から役立つ部分を拾っていっていただき、子育ての参考にしていただければ、とても嬉しいです。 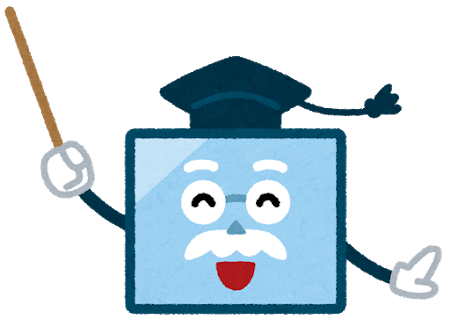 (take_futa)
(take_futa)
白(大).png)
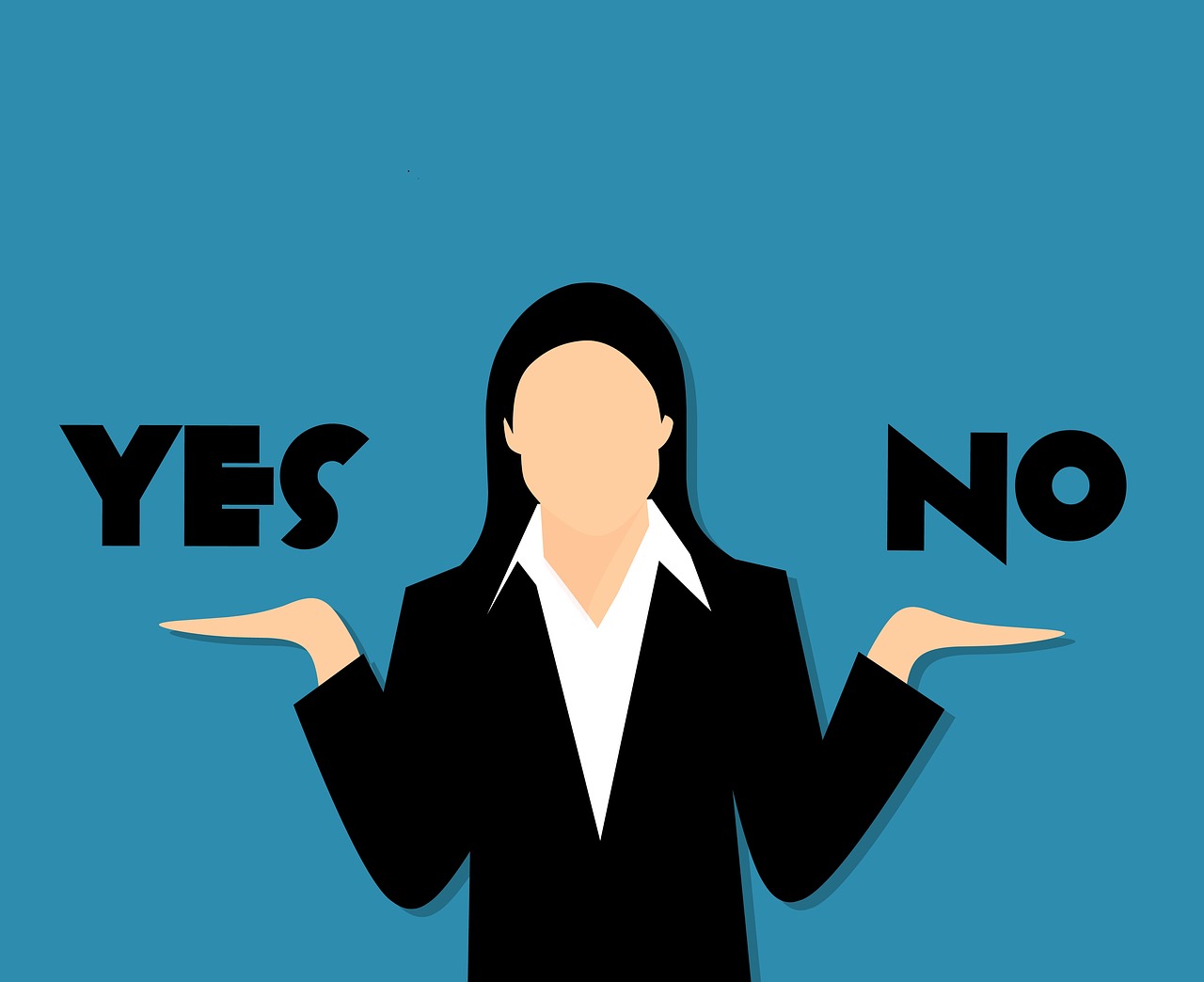
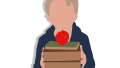

コメント