はじめに
 実は、中学受験を迷っている人は、塾に入るかどうかが、最初のハードルです。
実は、中学受験を迷っている人は、塾に入るかどうかが、最初のハードルです。
受験するかどうかも決まっていなかったり、低学年から準備しているというようなネットの書き込みを見ると、心配になるのもわかります。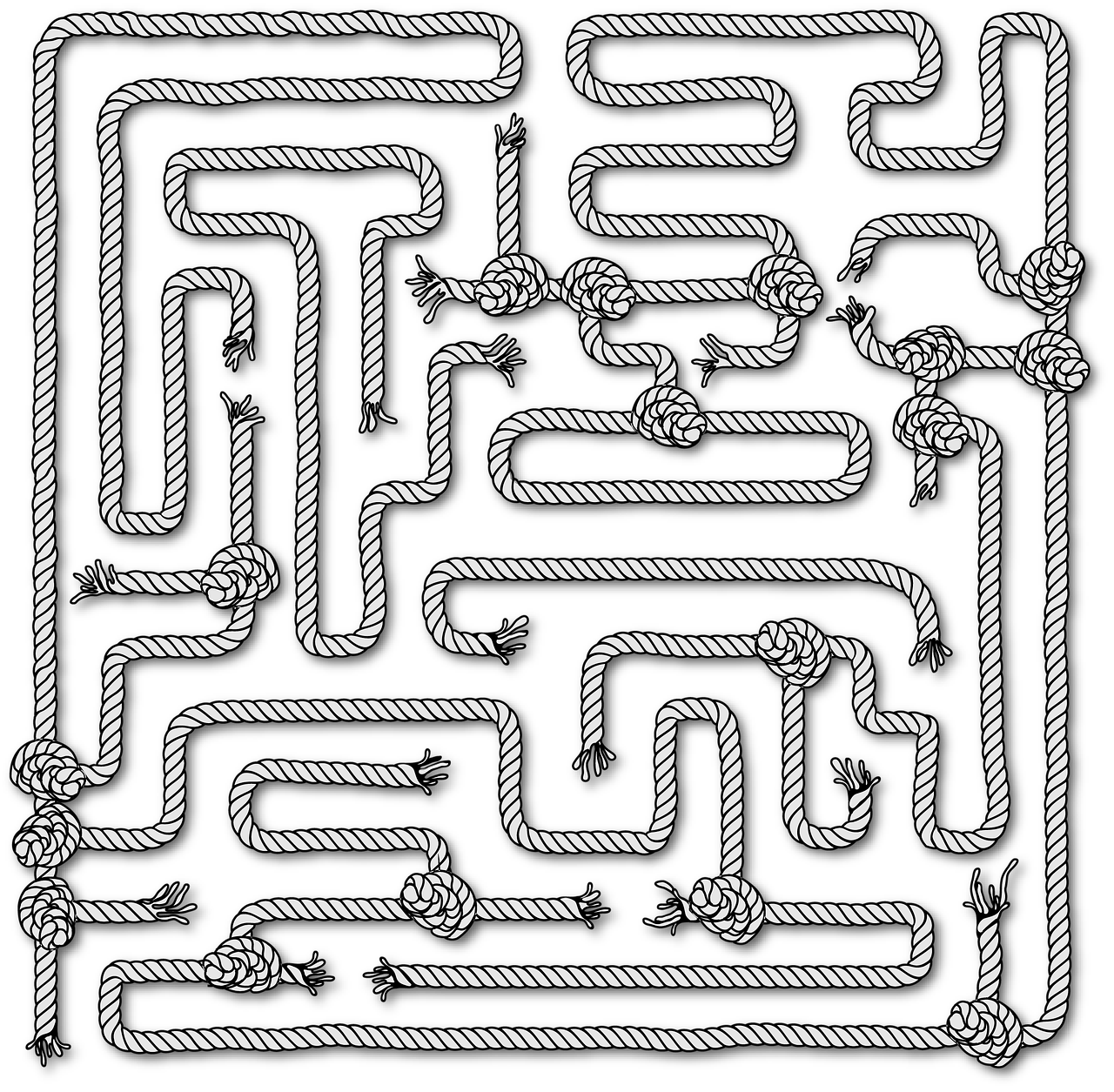 私は、プロフィールにも書いたように、進学塾での塾講師の経験が長いので、中学受験に迷う保護者・生徒を数多く見てきました。
私は、プロフィールにも書いたように、進学塾での塾講師の経験が長いので、中学受験に迷う保護者・生徒を数多く見てきました。
そこで、迷いを吹っ切れるようなアドバイスができればと思い、この記事を書くことにしました。
進学塾に入ってくるからと言って、必ずしも中学受験をするとはかぎりません。中には志望校を絞り込んで、計画的に入塾してくる生徒もいますが、小4まででは少数派です。
では、受験をするかどうかも分からないのに、生徒・保護者はなぜ入塾を考えるのでしょうか。私が見てきた「進学塾への入塾の目的」をいくつかのタイプに分けて、アドバイスを付け加えたいと思います。
進学塾を選ぶ理由
1)学校の勉強で困らないように
難度の高い前倒しの授業
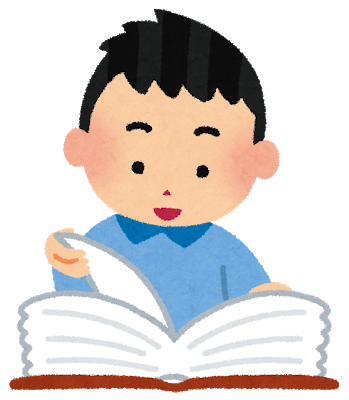 進学塾では基本的に前倒しの授業をしています。また、授業の難度も高く設定してあります。
進学塾では基本的に前倒しの授業をしています。また、授業の難度も高く設定してあります。
学校の勉強の予習になり、難しい問題にも慣れているので、学校のテストではかなり高得点が取れます。
ですから、学校の勉強で困ることはないという保護者の計算です。
学校レベルの基礎学力が必要
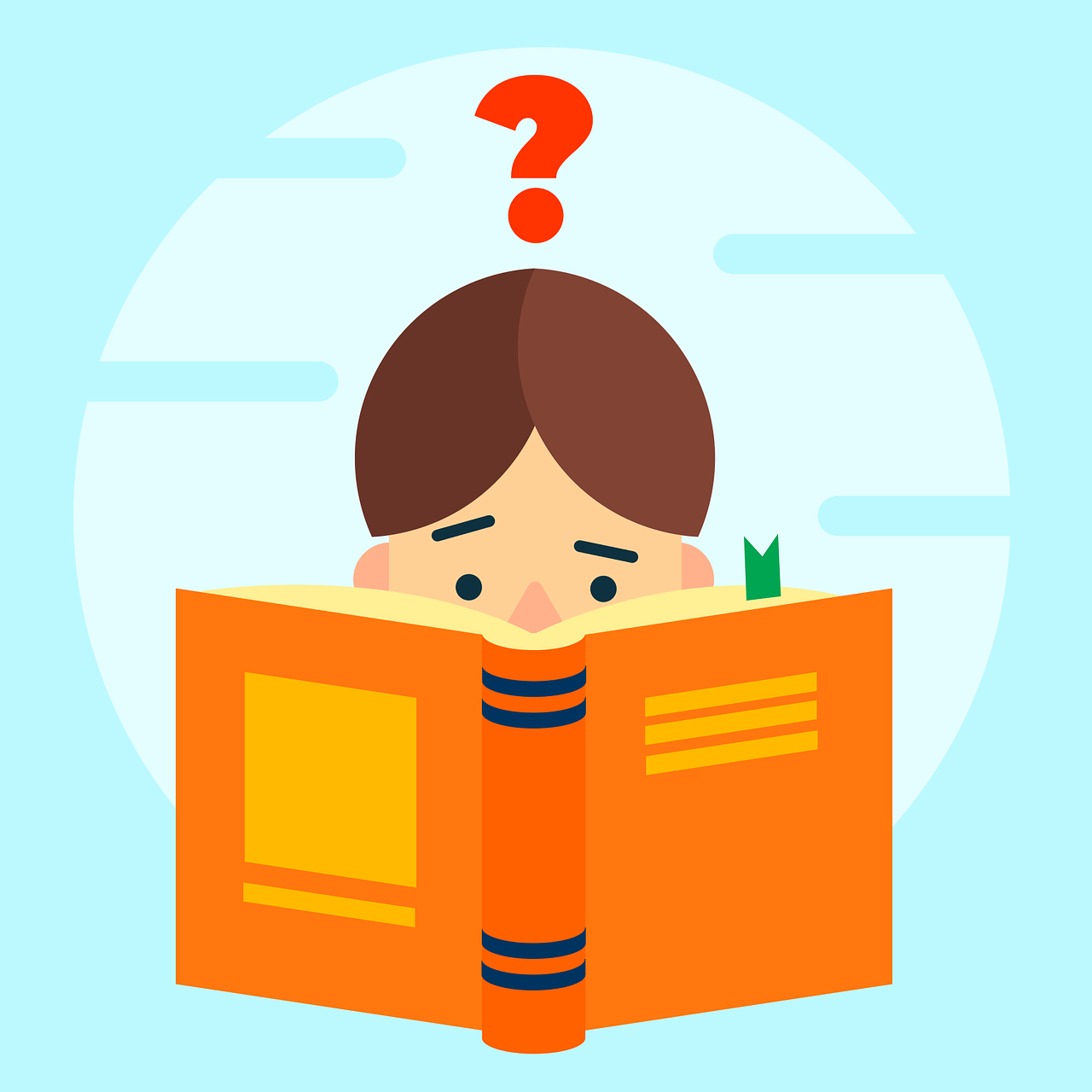 しかし、気をつけなければならないのは、学校の勉強で遅れを取った状況で、進学塾に入ると、学校の勉強と塾の勉強の板挟みになって、学校の成績が落ちてくるという本末転倒な結果になってしまいます。
しかし、気をつけなければならないのは、学校の勉強で遅れを取った状況で、進学塾に入ると、学校の勉強と塾の勉強の板挟みになって、学校の成績が落ちてくるという本末転倒な結果になってしまいます。
進学塾は、学校レベルの基礎ができている場合の選択肢になります。
2)学校の勉強では物足らないので、少しハイレベルの授業を受けさせたい。
学校の授業が「だるい」と感じる
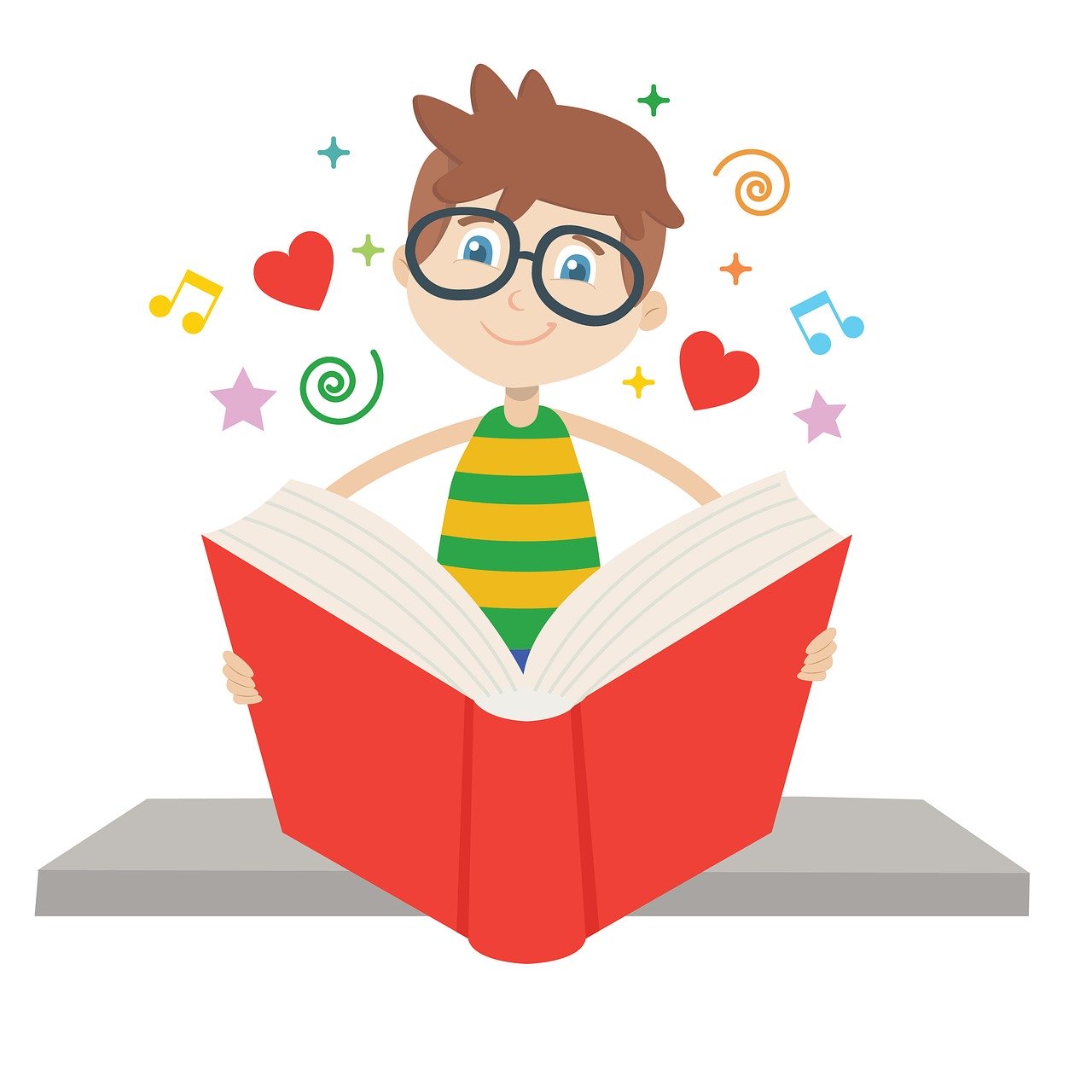 早熟の子や頭の回転の速い子は、学校の授業は物足りないと感じます。その上、学校では落ちこぼれを作らないために、一部の生徒用に時間を使います。そのような理由もあって、よけいにレベルや速度が「だるい」と感じるのではないでしょうか。しかし、学校は「人づくり」をする場所と認識しているので、今の日本のシステムでは仕方のないことだと思います。
早熟の子や頭の回転の速い子は、学校の授業は物足りないと感じます。その上、学校では落ちこぼれを作らないために、一部の生徒用に時間を使います。そのような理由もあって、よけいにレベルや速度が「だるい」と感じるのではないでしょうか。しかし、学校は「人づくり」をする場所と認識しているので、今の日本のシステムでは仕方のないことだと思います。
学力レベルをテストする塾が本物
 その点、進学塾は受験レベルの授業が前提なので、入塾時に「入塾テスト」を実施するのが一般的です。だからこそ、授業の質を高めることができるのです。仮に、入塾テストも「学力を示すテストの提出」も求められない塾があったとすると、授業の内容はあまり期待できないと思います。
その点、進学塾は受験レベルの授業が前提なので、入塾時に「入塾テスト」を実施するのが一般的です。だからこそ、授業の質を高めることができるのです。仮に、入塾テストも「学力を示すテストの提出」も求められない塾があったとすると、授業の内容はあまり期待できないと思います。
3)どこを受験するかまでは決めていないが、中学受験させたい。
受験校は決めていなくても大丈夫
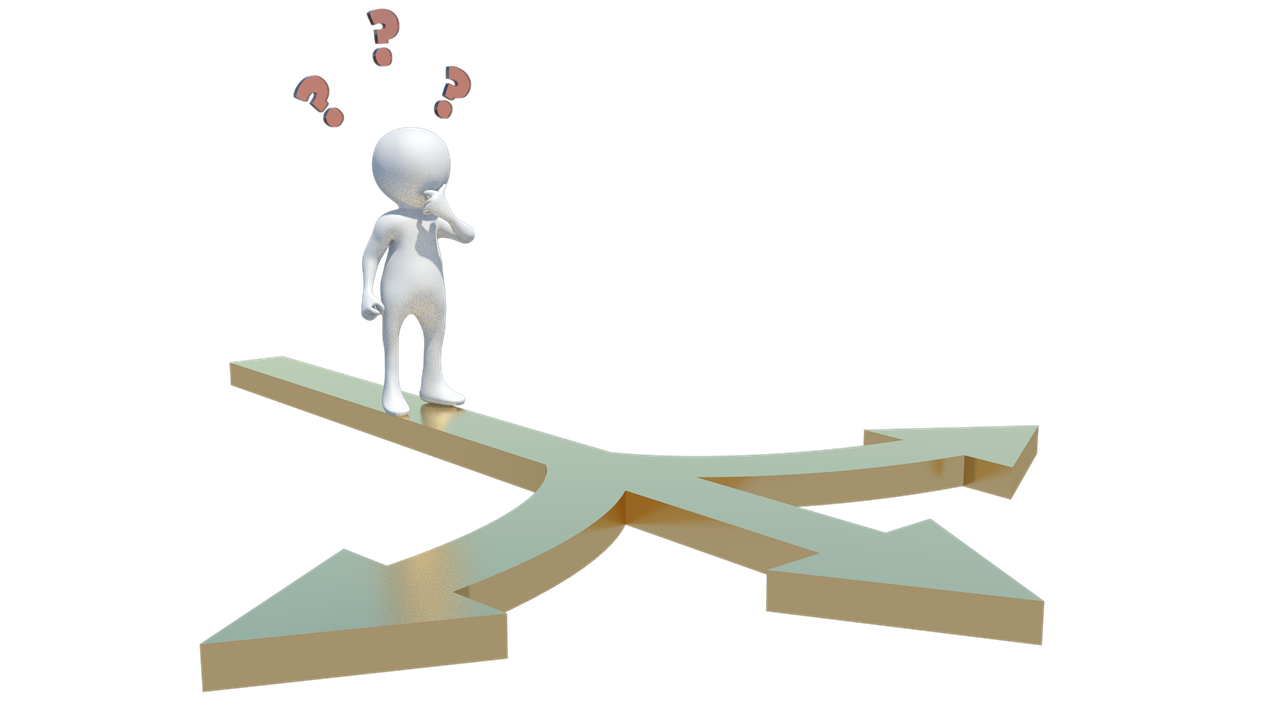 通常の私立・国立系中学の入試ならば、小学6年生になるまでに志望校を決めていれば大丈夫ですが、公立中高一貫校などで実施されている「適性検査」のような、特別な準備が必要な入試では、小5になるまでに決めておいた方がいいと思います。
通常の私立・国立系中学の入試ならば、小学6年生になるまでに志望校を決めていれば大丈夫ですが、公立中高一貫校などで実施されている「適性検査」のような、特別な準備が必要な入試では、小5になるまでに決めておいた方がいいと思います。
但し、入塾時の学力レベルが大きく足りない場合は、進学塾での勉強は本人の負担になると思います。中学受験は、「諸刃の剣」の側面を持つことをご理解ください。
小5までに小6内容を終えておく必要
また、まともな進学塾ならば、遅くとも小5までに小6の内容は終えています。あるレベル以上の受験塾に入るためには、小5までなら何とかなりますが、小5の夏休みを越えたところあたりから中途の入塾は厳しくなります。
目指すレベルがそれほど高くない場合は、小6からでも間に合うコースはあります。また、入塾までに自宅や、家庭教師などで前倒しの勉強をしていて、塾の進度に追いついていて、学力があれば、いつでも入塾は可能だと思います。
4)受験したい中学が明確に決まっていて、そこに合格するために入塾した。
志望校が決まっていれば具体的に対応できる
 進学塾にとっては、具体的な指導がしやすいケースです。受験中学向けの勉強法や問題集、その中学専門の特別講座など、ロードマップが作りやすいのです。
進学塾にとっては、具体的な指導がしやすいケースです。受験中学向けの勉強法や問題集、その中学専門の特別講座など、ロードマップが作りやすいのです。
気になるケース
しかし、少し気になるケースもあります。
親御さんが主導で受験中学を決めて、生徒さんの意思が入っていない場合です。
理由はいろいろあると思います。
例えば、ネットで調べて卒業生に一流の人が多いとか、評判が高いなどで親御さんが気に入ったからとか。
または、自分が通っていた中学に子どもを入れたいとか。
または、親御さんが子どものころその学校の受験に失敗したリベンジなどです。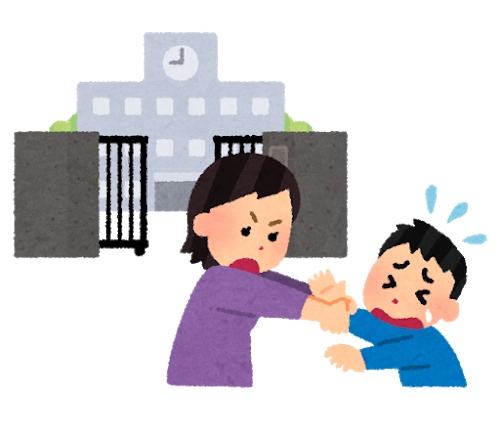 はたして、本人の意思は入っているのでしょうか。中学受験は家族の協力が必要なのは確かですが、受験勉強をするのはお子さんだということを、理解してください。お仕着せの勉強は全くモチベーションが上がらないことの方が多いと思います。
はたして、本人の意思は入っているのでしょうか。中学受験は家族の協力が必要なのは確かですが、受験勉強をするのはお子さんだということを、理解してください。お仕着せの勉強は全くモチベーションが上がらないことの方が多いと思います。
ただ、親の影響で本人もその中学に憧れを持ち、モチベーションが上がっていれば、問題はありませんが・・・。
5)受験するかしないかも決まっていないが、受験勉強が学力アップにつながると思ったから。
受験しなくても、受験勉強はプラスになる
学校の授業を問題なくこなせているのなら、進学塾の速く・応用のきいた問題もこなせる基礎力ができていると思います。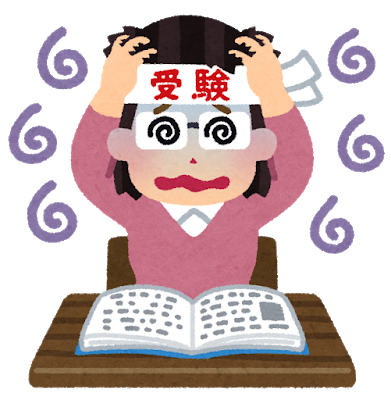 もし、そのような学力なら、進学塾での受験勉強をお勧めします。
もし、そのような学力なら、進学塾での受験勉強をお勧めします。
受験勉強というと、詰め込み式で、遊びも運動もすべて諦めるような、不健康なイメージがある方が、かなりいらっしゃると思います。しかし、それは30年も昔の話です。平成・令和の受験勉強はかなりスマートだと思ってください。
今の受験勉強は、弊害が解消されている
考える能力を鍛える
 知識やテクニックをひたすらインプットするのは昭和式です。今は、考える能力を鍛えるような勉強に変わってきています。特に、文科省の新教育改革(新学習指導要領、大学入試改革、公立中高一貫校の新設)などで、その方向性に拍車がかかっています。
知識やテクニックをひたすらインプットするのは昭和式です。今は、考える能力を鍛えるような勉強に変わってきています。特に、文科省の新教育改革(新学習指導要領、大学入試改革、公立中高一貫校の新設)などで、その方向性に拍車がかかっています。
時間をかけて受験準備をする
 以前は、小6になって初めて受験を考えるなど、受験勉強を始める時期が遅い傾向にあったので、無謀な受験計画になってしまいました。「無理して」受験勉強をするならまだましで、子どもにとって必要な運動や遊びまで我慢させる「無茶な」受験勉強になっていました。この傾向も、受験開始年齢の低年齢化で、解消されつつあります。
以前は、小6になって初めて受験を考えるなど、受験勉強を始める時期が遅い傾向にあったので、無謀な受験計画になってしまいました。「無理して」受験勉強をするならまだましで、子どもにとって必要な運動や遊びまで我慢させる「無茶な」受験勉強になっていました。この傾向も、受験開始年齢の低年齢化で、解消されつつあります。
受験にかける時間は、長いほうが計画的な学習計画が立てられるのです。
脳には、鍛えるのに適した時期が存在
小学生がラストチャンス
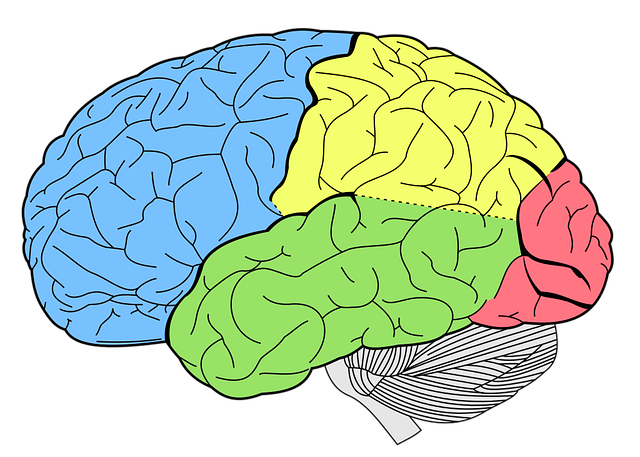 脳には、鍛えるのに適した時期が存在します。しかし、「6歳までに・・・」という、育脳教育業界のCMは少し極端だと、個人的には思っていますが、それでも「柔軟な思考力」をつけるのは、経験的に小学生時代がラストチャンスのような気がします。
脳には、鍛えるのに適した時期が存在します。しかし、「6歳までに・・・」という、育脳教育業界のCMは少し極端だと、個人的には思っていますが、それでも「柔軟な思考力」をつけるのは、経験的に小学生時代がラストチャンスのような気がします。
楽な勉強では負荷が足りない
 その大切な時期に、学校の勉強で物足りないと感じる子どもにとって、学校の勉強だけでは「楽すぎる」のです。能力はある程度の「負荷」がなければ伸びません。それは、スポーツでも芸術でも勉強でも同じです。
その大切な時期に、学校の勉強で物足りないと感じる子どもにとって、学校の勉強だけでは「楽すぎる」のです。能力はある程度の「負荷」がなければ伸びません。それは、スポーツでも芸術でも勉強でも同じです。
そのような時、受験勉強は適度な「負荷」になるのです。受験勉強をした中1生と、しなかった中1生を比べると、その差に驚きます。実は、受験の合否に関係なく受験勉強をした生徒の学力は質的に全く違うのです。
ですから、最終的に受験はしなくてもいいので、受験勉強だけは経験させてあげることをお勧めします。
最後に
中学受験は、みんながするから自分もする、というようなものではありません。
受験勉強を始めるには、基礎学力が必要です。
また、簡単に合格するとは思わないでください。通常2倍以上の倍率がありますから、半分以上は合格できないことも、覚悟しておく必要があります。
学校で成績がいいからといって、必ずしも受験の基礎学力ができているとは限りません。入塾時に入塾テストを受け、塾の担当の先生や塾長先生ときちんとお話をしてみた方がいいと思います。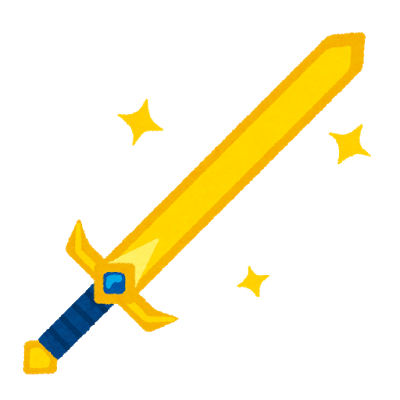 中学受験は上で述べたように、受験勉強をするだけでも役に立つのですが、諸刃の剣の側面を持つことを再度アドバイス致します。
中学受験は上で述べたように、受験勉強をするだけでも役に立つのですが、諸刃の剣の側面を持つことを再度アドバイス致します。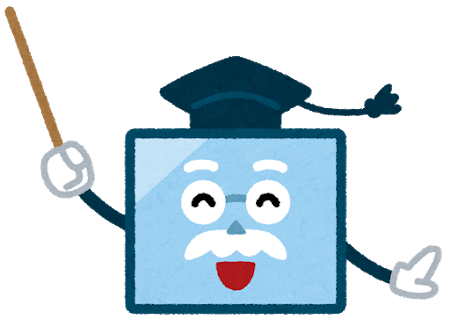 (take_futa)
(take_futa)
白(大).png)


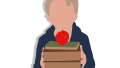
コメント