はじめに
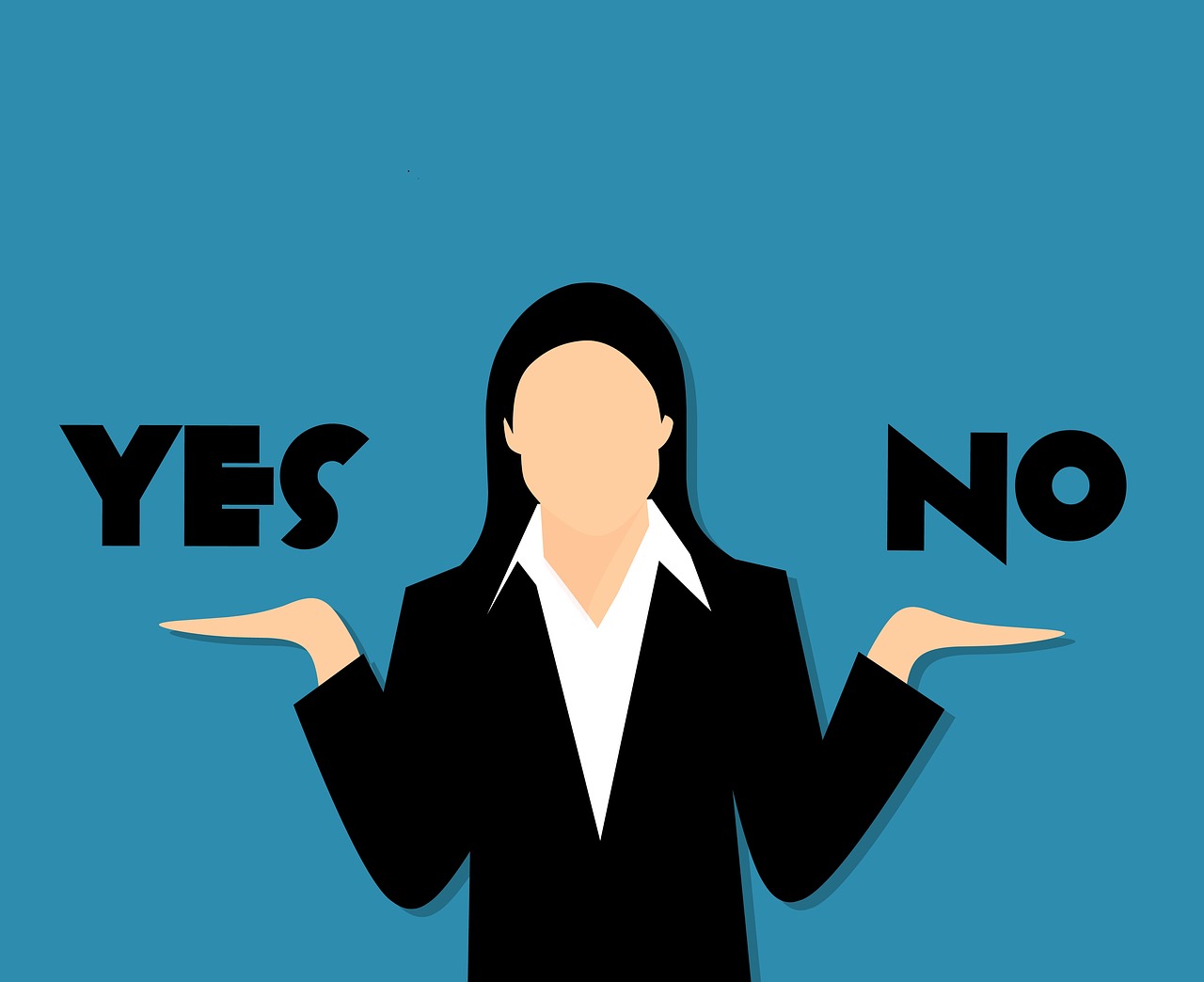 以前、「褒めて育てるとは」という私の記事で、「子どもをダメにする親」に触れたことがありました。そして、調べていく中で、もう少し子どものことを考えて育てていたら、子どもの人生が違っていたのにと思うケースに数多く出会いました。子どもには罪がないのに、親の育て方で子どもがダメになってしまうことが、残念で仕方ありません。
以前、「褒めて育てるとは」という私の記事で、「子どもをダメにする親」に触れたことがありました。そして、調べていく中で、もう少し子どものことを考えて育てていたら、子どもの人生が違っていたのにと思うケースに数多く出会いました。子どもには罪がないのに、親の育て方で子どもがダメになってしまうことが、残念で仕方ありません。
この記事では、「子どもをダメにする親」に焦点を当てて、深堀してみたいと思います。しかし、子どもをダメにする親の共通点や、パターンを挙げて、現在進行形で子育てをしている方を責める気持ちは毛頭ありません。逆に、誤った方向に歩いていると気付いた親御さんに、方向修正していただくことが、この記事の目的です。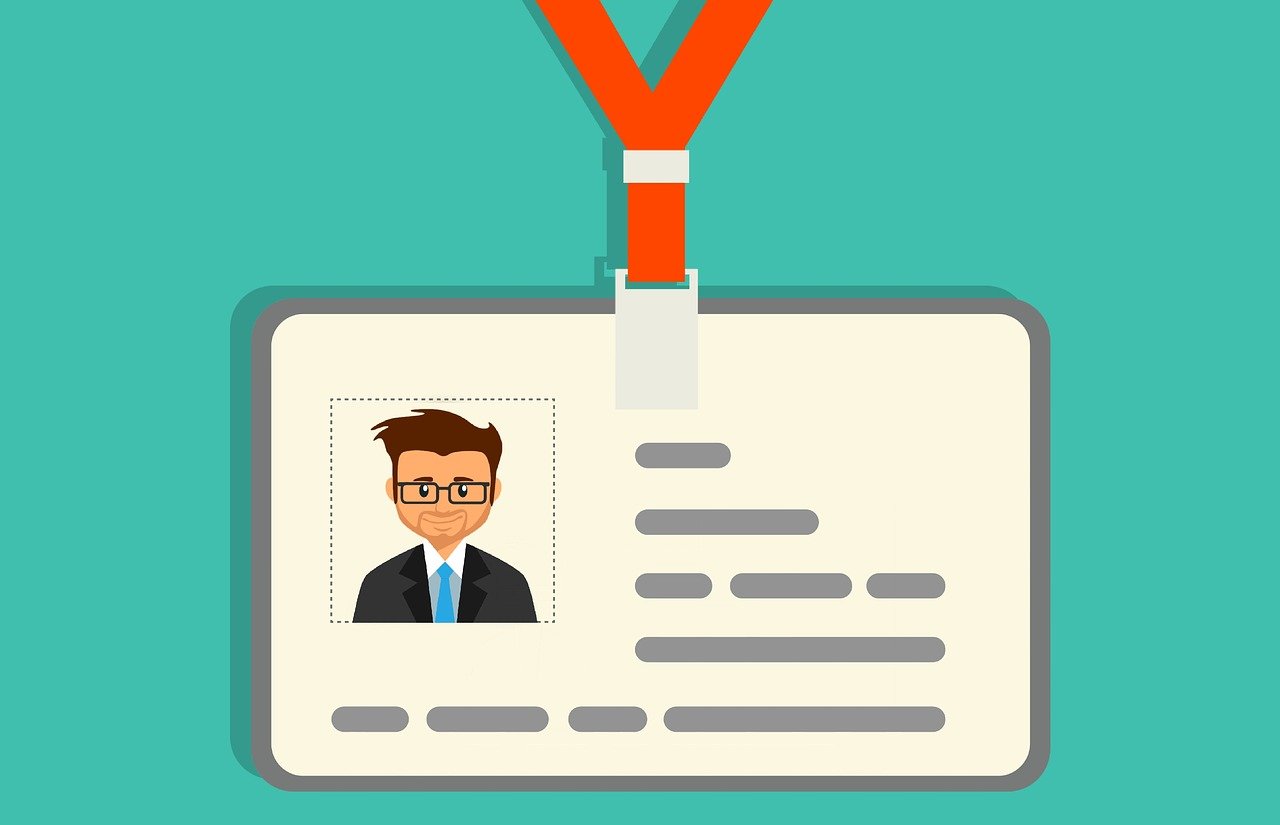 気付いた時が出発点です。子育ては、みんな無免許運転なのですから、良かれと思ってやっていても 、間違うことは山ほどあるのです。間違うことは悪くないのです。気付いたら、方向修正をしましょう。遅すぎることはありません。
気付いた時が出発点です。子育ては、みんな無免許運転なのですから、良かれと思ってやっていても 、間違うことは山ほどあるのです。間違うことは悪くないのです。気付いたら、方向修正をしましょう。遅すぎることはありません。
「子どもをダメにする親」の分類
対極にある親の傾向
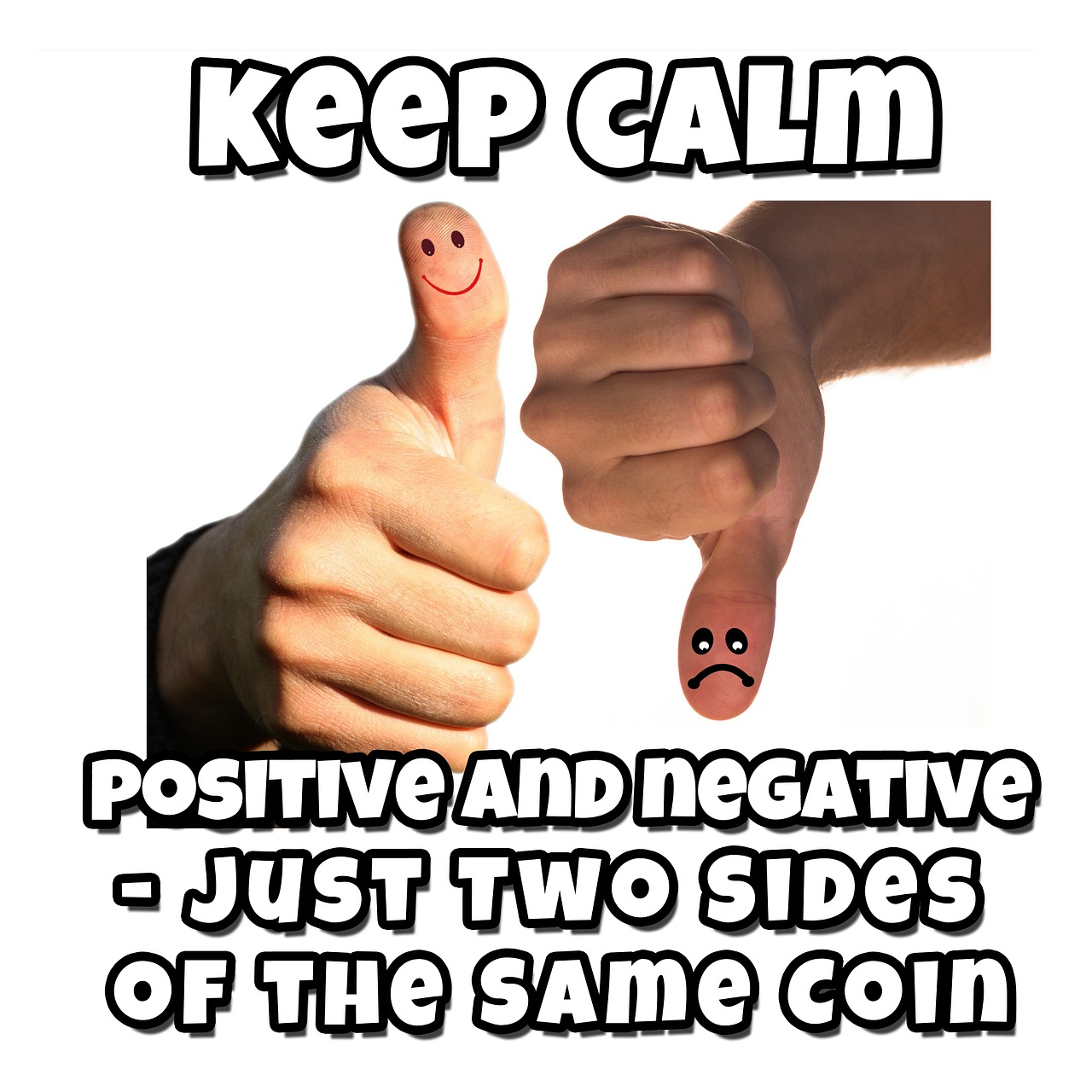 「子どもをダメにする親」のタイプを私なりにまとめてみました。そして、対極にある親のタイプを左右に分けて並べて見てみると、必ずしも片方が「子どものために良く」て、その対極が「子どもをダメにする」という図式にはならないことが、分かりました。見てみましょう。
「子どもをダメにする親」のタイプを私なりにまとめてみました。そして、対極にある親のタイプを左右に分けて並べて見てみると、必ずしも片方が「子どものために良く」て、その対極が「子どもをダメにする」という図式にはならないことが、分かりました。見てみましょう。
子どもに近い ⇔ 子どもから遠い
 近すぎるとヘリコプターペアレントなど、子どものそばで管理・干渉し続ける親。その結果、やる気を失ったり、自主性のない子どもになります。
近すぎるとヘリコプターペアレントなど、子どものそばで管理・干渉し続ける親。その結果、やる気を失ったり、自主性のない子どもになります。
遠すぎると、放任・放置・育児放棄になってしまいます。
子どもに命じる ⇔ 子どもの言いなり
 子どもへの命令が行き過ぎると、自分で判断できない子どもになります。
子どもへの命令が行き過ぎると、自分で判断できない子どもになります。
親が自分で判断しないことが多いと、子どもが暴君化します。
バツを与える ⇔ ご褒美を与える
バツを与えれば、恐怖のため一時的に改善しますが、そのこと自体を嫌いになる傾向があります。 ご褒美を与えすぎれば、ご褒美が目的になってくる傾向があります。
ご褒美を与えすぎれば、ご褒美が目的になってくる傾向があります。
人として尊敬できる ⇔ 人として軽蔑される
子どもはちゃんと人を見ています。尊敬できる人間か軽蔑すべき人間かは、見極めています。そして、軽蔑する人間の言うことには聞く耳を持たないのです。子どもは論理的な脳は未熟ですが、感覚は大人と変わらないのです。
実は、尊敬できる親の場合には、問題がないように見えますが、「立派過ぎる親」を持つ子どもの中には、かなりの割合で、自分を矮小化しているケースを見かけます。
子どもを一人の人として扱う ⇔ 子どもを自分の所有物として扱う
子どもを一人の人として扱うならば、子どもの意見を聞き、お互いの希望を調節して、どうすべきかを決めます。 しかし、子どもが自分の所有物と思っているのなら、親がしたいように子どもを動かすだけなので、子どもの意思が入る余地はありません。
しかし、子どもが自分の所有物と思っているのなら、親がしたいように子どもを動かすだけなので、子どもの意思が入る余地はありません。
子どもは一人の人として扱われると、自分が認められていると実感できるので、モチベーションも上がり、自分に自信が持てます。
しかし、この場合も状況によっては、マイナスに働いてしまうことがあります。それは、年齢的に(精神的に)子どもが未熟な場合です。一人前の人間と扱われても、荷が重く困ってしまう子どももいるのです。見極めが大切になります。
子どもの良い面を見る ⇔ 子どもの悪い面を見る
 子どもの良い面を見ると、褒める回数が増え、子どもに自信を与えます。
子どもの良い面を見ると、褒める回数が増え、子どもに自信を与えます。
子どもの悪い面を見ると、叱る回数が増え、叱られた事がよけい嫌いになり、自信を失います。
しかし、どちらも極端になってはいけません。なんでもかんでも褒めるのはマイナスだということの深堀は、私の記事の「褒めて育てるとは」をご覧ください。
子どもに挑戦させる ⇔ 子どもの代わりにやってしまう
 子どもができないと思うようなことでも、子どもが望めばやらせてみると、難しいことに挑戦する気質ができます。
子どもができないと思うようなことでも、子どもが望めばやらせてみると、難しいことに挑戦する気質ができます。
親が代わりにやってしまっては、高い山には登らない気質が出来上がります。つまり、難しいことに挑戦しなくなるのです。
しかし、子どもに挑戦させてみたけれど、やはり難しくてできないことはあります。そのような場合は、実は手伝って仕上げてもいいのですが、そのところを勘違いして、挑戦させるだけさせて、最後に無理だとわかった時、手伝いもせずに「できるまで挑戦させる」方針を貫く親御さんがいます。
結局、途中で挫折してフォローもおろそかだった場合には、子どもの自信を失わせることにつながるのです。
性格がルーズ ⇔ 性格が几帳面
これも両極端は子どもにとって悪い影響があります。親が後片付けができず、ゴミ屋敷だったり、几帳面過ぎて幼児のうちから服を汚す遊びを親が嫌がったりするのは、完全に親都合です。 家がゴミ屋敷だった場合、衛生上の問題はもちろんありますが、片付けるという概念が育たないことの影響も大きいと思います。
家がゴミ屋敷だった場合、衛生上の問題はもちろんありますが、片付けるという概念が育たないことの影響も大きいと思います。 逆に几帳面過ぎて、子どもの服が汚れたり、机に落書きをしたりすることに耐えられず、子どもを強く叱ってしまうのも、行き過ぎは気になります。
逆に几帳面過ぎて、子どもの服が汚れたり、机に落書きをしたりすることに耐えられず、子どもを強く叱ってしまうのも、行き過ぎは気になります。
子どもの育てなくてはならない皮膚感覚が育たなかったり、自由な発想ができなくなったりと、少なからず影響があります。
しかし、ルーズとか几帳面とかいうのは、その人の性格・性質に関係したことなので、自分を変えようとする努力は、ストレスになるので無理はしないでください。
ただ、いつも「この自分のやっている行動は、子どもにどんな影響を与えているのか?」を思い出すようにしてください。はっと、気付いたときにやめるだけでも、違うと思います。
極端な子育てを避けましょう
「対極にある親の傾向」を見ていただきましたが、殆どが左右両極端に問題があるのです。つまり、極端な子育てに問題があることがわかりました。 例えば、「子どもの良い面を見る」と「子どもの悪い面を見る」では、「子どもの良い面を見る」方が正しいと、多くの人が思うのではないでしょうか。しかし、子育てに「一元論」は似合わないのです。良い面を見ることにこだわりすぎると、褒めるために叱ることをためらってしまうのは、よくあることです。
例えば、「子どもの良い面を見る」と「子どもの悪い面を見る」では、「子どもの良い面を見る」方が正しいと、多くの人が思うのではないでしょうか。しかし、子育てに「一元論」は似合わないのです。良い面を見ることにこだわりすぎると、褒めるために叱ることをためらってしまうのは、よくあることです。
大切なので再度言います。子育てに「一元論」は似合いません。
子育てのゴールは「親子の自立」です
立正大学教授 臨床心理士 宮城まり子氏の文から引用させていただきます。
<自立のための5条件>
子どもの自立のための5条件を考えてみましょう。
心身の健康
 家族一緒に食を共にする「食育」も大切です。大切なのは身体とともに食事を通して心も豊かに育てることです。家での食事の風景の絵を子どもに描かせると、「孤食」の絵が多いことに驚きます。思春期になり心の病気がさまざまに表面化する子どもがいる原因の一つかもしれません。
家族一緒に食を共にする「食育」も大切です。大切なのは身体とともに食事を通して心も豊かに育てることです。家での食事の風景の絵を子どもに描かせると、「孤食」の絵が多いことに驚きます。思春期になり心の病気がさまざまに表面化する子どもがいる原因の一つかもしれません。
身辺生活の自立
 自分の身の回りのことは自分で管理できることです。「家庭の役割」とは何でしょうか。それは、何よりもまず子どもたちに「生活を教える」ことではないでしょうか。
自分の身の回りのことは自分で管理できることです。「家庭の役割」とは何でしょうか。それは、何よりもまず子どもたちに「生活を教える」ことではないでしょうか。
精神的自立
人に頼らず、自分自身で考え判断し行動する力です。いつか子どもは親から離れて、自分で問題を解決しなければなりません。そのためには、幼い時から子どもに考える力、問題解決する力をつける訓練が必要です。親が先回りして、指示している限り、子どもの考える力を鍛えることはできません。
豊かな人間関係を結ぶ力
 社会は人間関係から成り立っています。「対人能力」は社会のなかで自立して生きるために不可欠の能力です。相手と情況に合わせて柔軟に適切なコミュニケーションがとれて初めて、多様な人間関係が結べるのです。
社会は人間関係から成り立っています。「対人能力」は社会のなかで自立して生きるために不可欠の能力です。相手と情況に合わせて柔軟に適切なコミュニケーションがとれて初めて、多様な人間関係が結べるのです。
経済的自立
 最終的な自立は経済的な自立です。そして、最終的に経済的な自立は精神的自立を支える条件となります。そのためには、自分はどのような仕事を通して社会に貢献し、その役割と責任を果たすのか、自分の興味・関心のある仕事は何かなどを家族で一緒に話し合い考える機会をもつことは大切です。
最終的な自立は経済的な自立です。そして、最終的に経済的な自立は精神的自立を支える条件となります。そのためには、自分はどのような仕事を通して社会に貢献し、その役割と責任を果たすのか、自分の興味・関心のある仕事は何かなどを家族で一緒に話し合い考える機会をもつことは大切です。
最後に
「親子の自立」についてのどの項目を見ても、子育てのヒントがいっぱい隠れています。この記事のタイトルは「子どもをダメにする親」ですが、この記事の最終的な目的は「親子の自立」なのです。子どもをダメにしてしまった多くの方の反省がこの記事を作っています。子育てで悩んでいる方のヒントになれば幸いです。 (take_futa)
白(大).png)
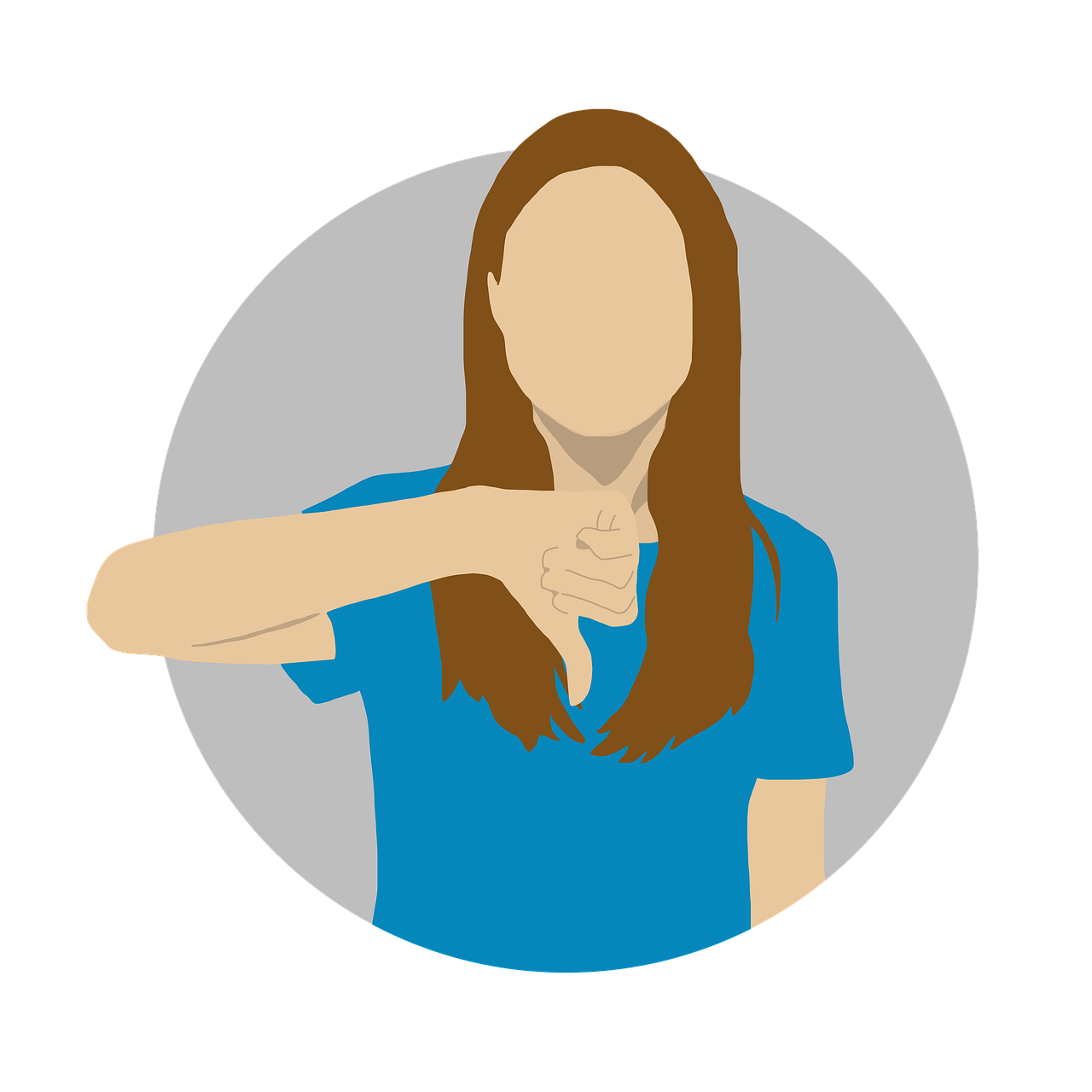


コメント